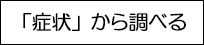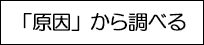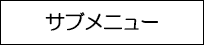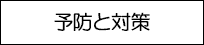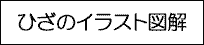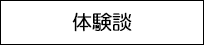有痛性分裂膝蓋骨でひざが痛むケース
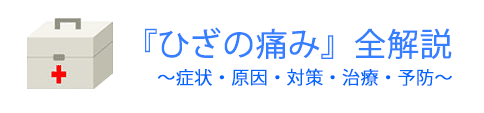
有痛性分裂膝蓋骨とは(症状・原因・治療)
膝の痛みを引き起こす可能性のある障害や病気の一つに「有痛性分裂膝蓋骨(ゆうつうせいぶんれつしつがいこつ)」があります。
ここでは膝の痛みとの関係を交えながら解説します。
1.有痛性分裂膝蓋骨が疑われる症状
膝の痛みのほかに以下のような特徴や症状が見られる場合、有痛性分裂膝蓋骨が発症している可能性があります。
|
痛みは膝の曲げ伸ばしをしたり、膝蓋骨に圧力がかかった時に発生し、膝を使わずに安静にしていると治まってきます。
症状が似ている膝の障害に膝蓋大腿関節症や膝蓋軟骨軟化症があります。
【参考】
2.有痛性分裂膝蓋骨とは ~ 特徴や原因
膝蓋骨(ひざの皿)は通常一つの状態ですが、まれに皿が割れたように2個以上に分裂している人がいます。こうした症状を「分裂膝蓋骨」と言い、特に痛みも伴うものを有痛性分裂膝蓋骨と呼びます。
◆原因
膝蓋骨の分裂はそのほとんどが生まれつき見られる「先天性」のものですが、膝蓋骨に衝撃が加わって皿が割れるケースもあります。スポーツ時に膝蓋骨に付着している太もも前面の筋肉(大腿四頭筋)によって何度も引っぱられて負荷が蓄積したり、事故や転倒などの怪我で膝を強くぶつけた時などです。
◆どんな時に痛むのか
皿が分裂していること自体が痛みの原因ではないため、痛みなどの症状が全く出ない場合のほうが多いです。しかし激しいスポーツや運動を行った時や、しゃがみ動作を多く行った時などに、膝蓋骨の分裂した部分に大きな負担が加わることで炎症が発生すると痛みが生じます。
急激なダッシュや急停止など、特に太ももの筋肉(大腿四頭筋)を酷使するスポーツで痛みが発症するケースが多く、ほかにも成長期にあって骨や筋肉の成長が著しく膝が不安定になりやすい10代前半(小学生高学年~中学生)の男子に多く見られます。
<痛みが発生しやすいスポーツ>
- 野球、サッカー、バレーボール、バスケットボール、陸上競技(特に短距離走)
3.診断・治療・予防
◆診断
X線撮影(レントゲン)やCTスキャンなどの画像検査で、分裂した膝蓋骨が確認できます。
◆治療・予防
症状が軽度であれば、痛みが治まるまで運動を中止して安静を保つことで自然と痛みは治まります。
より積極的な治療では、炎症を抑え膝の負担を軽減するための保存的療法が主となります。炎症を抑える目的では、患部を温める温熱療法や、消炎鎮痛剤入りのシップ薬や塗り薬による薬物療法がとられます。膝の負担を軽くするには、膝をテーピングやサポーターで固定する装具療法、膝周辺の筋肉を鍛える運動療法が効果的です。
【関連項目】
運動中に急に痛みが発生した場合は、膝を氷のうなどで冷やすのが良く、痛みが長引いて慢性化している時は逆に入浴やカイロで温めるようにしましょう。(参考:温熱療法)
こうした治療法では痛みが治まらなかったり、何度も痛みの再発を繰り返す時は、膝蓋骨の一部を摘出または縫合する(くっつける)手術が行われます。
予防法としては、膝の負担を減らすことが第一です。
運動前後のウォームアップとクールダウンはしっかり行い、「膝を急激に動かす」、「ジャンプ動作を繰り返し行う」、「長時間のランニングを行う」など、膝を酷使する無理な運動は避けましょう。膝の疲れや違和感を感じたら、回復するまでしっかりと休養をとるよう心がけましょう。
膝蓋骨への負担を減らすには、太もも前面の大腿四頭筋の強化が有効です。筋力トレーニングとストレッチングを定期的に行い、筋力と柔軟性を高めると発症を抑えられます。